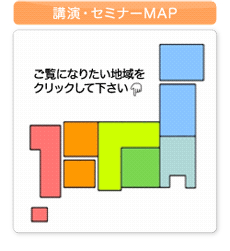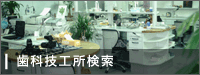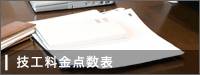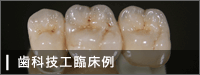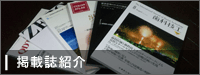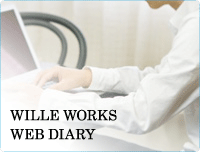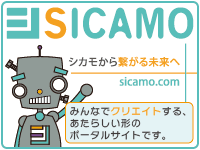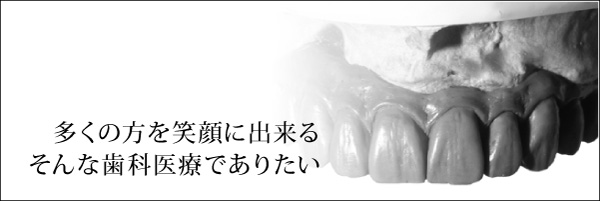(1)有史以前の古代
・魔法医学
病気は神の意思に因って生ずるものとした
→シャーマン(みこ)、医人
(2)有史以後の古代〜中世
○大和、飛鳥、白鳳時代(4〜7C)
・朝鮮、中国との交通を通して医師が渡来
・百済より仏教伝来(A.D.538)
・遣隋使:小野妹子(推古天皇- 日本最初の女帝)
→外国の医術が日本にもたらされた
○奈良時代(694〜794年)
・大宝律令の制定(701年):日本最初の医療制度
・遣唐使
・鑑真和上:仏教医学を伝える。
→歯科は耳、目、口、歯科の一部として存在したにすぎない
○平安時代(794〜1191年)
・仏教が盛んとなり、唐方医学が発達
高位の人々の疾病に祈祷がおこなわれる →奈良薬師寺
・丹波康頼:「医心方」 →現在存在する最古の医学書。日本医学の祖
○鎌倉時代(1192〜1333年)
・医学は僧侶の手にうつる。(僧医)
・中国医学の影響を受け普及
・丹波冬頼:花園天皇の歯を抜歯
○室町時代(1334〜1573年)
・丹波兼康:口中科の元祖
→わが国の中世(平安、鎌倉、室町時代)の歯学は医学の分野として独立した形態をとるようになる
(3)近世
○江戸時代(1603〜1867年)
・朝廷、幕府、藩に勤務する口科医。
・民間渡世の入歯師、入歯渡世者、歯抜き
※鎖国令:1633年〜開国1859年(226年間)
(4)明治時代(1868〜1911年)
→わが国の歯科医学は、幕末から明治の初期に来日した外国人、または外国で歯科医学を学んだ日本人によって移植された。(19世紀中期頃)
→主としてアメリカ人歯科医の来期によるものである。
・ウイリアム・クラーク・イーストレーキ(アメリカ人)
日本に渡来した最初の外国人歯科医師。
わが国の歯学発展に多くの指導的な役割を果たした。
わが国の歯科医学はアメリカの歯科医学に影響を多大に受けて発展し、現代に至る・・・
【この記事を読んだ方におすすめ】
・ 歯科技工士の感染症について
・ 過去のアスベスト被害
・ 歯科技工料金点数表
・ 歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針